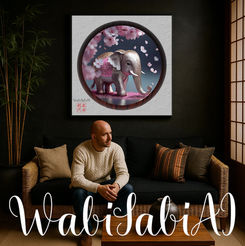私は「AIと人の感性と融合し未来を創造するクリエイティブイノベーター」のHIROYOです。技術に「愛・感動・癒し・文化・金融」を加え、独自の視点でサービスを展開しています。
そんな私は音楽大学卒業後、就職で失敗し、社会人生活はアルバイトからスタートしました。順風満帆とはいかない苦労の連続の起業ストーリーです。
<略歴>
武蔵野音楽大学及び慶應義塾大学法学部(通信教育)卒業、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科(MBA)退学。沖電気工業株式会社、株式会社ゴールデンチャート・エー・エム・エス(投資助言業の代表取締役)などを経てM3WEを起業。Adobe歴は20年以上とクリエイティブの経験も長い。経営、商品の企画、マーケティング、金融記事の執筆、業務効率化、DTP、セミナー企画・講師、経理、コンプライアンスなどさまざまな業務を経験。起業後はNFT、AIアート、AI音楽、株式投資の本の出版などを行う。
note
起業ストーリー
高校&大学の進学先は、ピアノと英語から選択
私は3歳半からピアノを習い始めました。学習塾、生け花などをはじめ、習い事の一つとしてです。そして高校を進学する際に、将来は「音楽大学に行く」と決めていました。ピアノが好きで決めたわけではありません。親から「音楽か英語のどちらかで進学しなさい」と言われ、高校と大学名を具体的に挙げられました。音楽なら「県内の音楽科と武蔵野音楽大学」、英語なら「県内で英語の強い高校と東京の語学で有名な大学」です。選択肢はその2つしかないのです。中学生の私は考えました。「英語の強い高校に行くことができるほどの頭はない。でも音楽ならすでに持っている技術力で入学できそう」と。そんなわけで、確実に進学できる音楽科のある高校を選びました。田舎暮らしだったので、もちろん「ピアノを頑張れば東京に行くことができる」という楽しみもありました。
進学した高校は、当時1学年10クラスほどある学校でした。その中で、音楽科は学年に1クラスでした。授業は一般的な教科に加え、ピアノの演奏、声楽、合唱、そして音楽の専門教科です。受験に必要な専門知識も学びました。それまで知らなかったことをたくさん学び、「やっぱり専門的な場で学ぶと違うな」と思ったことを記憶しています。
高校時代は3年間寮生活でした。上下関係は厳しかったですが、同級生との暮らしはとても楽しかったです。
音楽大学の入試は勉強も大事ですが実技重視です。ピアノはあまり好きではなかったですが、入学に必要な実技は十分身につけることができました。そして無事に武蔵野音楽大学に入学しました。
武蔵野音楽大学は、全国から本当に音楽が好きな人が集まる場でした。高校までとは違い、みんなレベルが高いのです。特に武蔵野音楽大学の付属高校から上がってきた人たちは熱意も技術力も違いました。「別世界だ」と感じたものです。
1、2年生は入間の校舎でした。ここは山の中に校舎と寮があります。普段は学校の敷地の外に出ることなく生活します。ピアノの練習室のある棟からは朝から晩までずっとピアノの音が鳴り響いていました。寮生活をしていた私は授業が終わると、そのままピアノの練習に行きます。そして夜は寮に戻り友達と夕食を食べ、お風呂に入り、部屋で過ごします。音楽漬けの暮らしでした。
当時の音楽大学生は「お金持ちの家の女性が通う」というイメージが強い時代でした。共学の大学でしたが、女性の比率が圧倒的に高かったものです。卒業後は学校の先生やピアノの先生、またはプロを目指す人もいましたが、一方で実家に帰るという人が多くいました。私も入学する時に両親に「卒業したら実家に帰ってきて家でピアノを教えればいい」と言われていました。
大学生になり「本当にやりたいこと」を探し始める
寮生は、夏休みなどの長期休暇になると寮に住むことができません。休暇になると私は実家に帰っていました。家ではピアノの練習をしたり、寮ではできない家事をして過ごしました。私は料理が好きだったので、キッチンに立ち凝った料理やケーキなどのデザートを作って楽しんでいました。当時は今のように時短グッズなどもありません。下ごしらえをしたり煮込んだりしていると、あっという間に数時間経っていました。寮にはキッチンどころか冷蔵庫もありませんでした。だから実家での料理は楽しかったのです。しかしそこで気づいたのです。キッチンに立ち、夕食後の片付けをして1日が終わると、「もしこのまま専業主婦になったら、私の人生は家事だけで終わってしまうではないか」と。つまり社会に対して生きている証が何も残らないと思ったのです。そんな人生は悲しいなと感じました。そこで私は「卒業後は就職しよう」と思いました。私が初めて自分の人生について、自分で決断したことです。両親は、私の「就職したい」という気持ちに対して反対することはなくサポートしてくれました。
クラシック音楽といえば、「楽譜通りに演奏する」ことが大前提です。小中学校の音楽の授業でも、楽譜通りに歌ったり演奏しなければなりません。それと同じです。しかし私は「楽譜通りに弾かなければならない」ということが得意ではありませんでした。小さい頃から自由に弾きたかったのです。しかし小学生の頃から自由に弾くことは「練習ではない」ということで怒られていました。勉強なら隠れて自分の好きなものを学ぶことができます。しかしピアノの場合、音が出てしまうので、違う曲を弾いていたらすぐに周りの人にバレます。小さい頃からグランドピアノで練習していたので、すぐにバレて怒られていました。だから自由に弾くことはできませんでした。私はとにかく「自由に表現した」と思いマスコミを目指しました。それから、マスコミ向けの講座に通い、就職活動の準備を始めました。
しかし、マスコミへの就職は難関でした。もちろん背景に就職氷河期というのもあったかもしれません。当時、音楽大学から一般企業への就職は少なかったものです。大学の就職課に相談したものの「自分でやってください」と言われてしまい、結局大学を頼ることなく、一人で活動することになりました。テレビ局、新聞社、出版社などを受けました。最終面接までいった企業があったものの内定を貰うことはできず、結局就職浪人をすることになりました。
就職活動に失敗し、長期アルバイトの仕事に就く
大学卒業後、再度既卒でマスコミに挑戦しました。しかし次もうまくいきませんでした。そこで、しばらくの間、短時間のアルバイトなどをしながら過ごしました。しかしずっとこれではいけません。そこで長期のフルタイムに近い働き方のするアルバイトを探しました。なぜなら、まだマスコミに就職する夢を諦めていなかったからです。そこで出会ったのがDTP(デスクトップパブリッシング=雑誌などの誌面の制作・デザイン)の仕事です。当時はまだWebサイトはあまりなく、情報といえば雑誌の時代でした。
ここから私のクリエイティブ人生がスタートしました。私の仕事は雑誌の制作進行でした。基本的には制作に関する管理です。しかし制作そのものにも関与できたので、挑戦しました。当時はまだパソコンが使えなくても就職できた時代です。私はこの会社でMac、Adobe PhotoshopやIllustrator、DTPでの誌面制作、雑誌の制作フローなど学びました。
最初は専門誌を担当しましたが、途中から当時なら誰でも知る雑誌を担当することになりました。書店で自分が関与した雑誌が並ぶのを見ると嬉しかったものです。
同年代の仲間がたくさんいて、楽しい職場でした。アルバイトなのに色々なことに挑戦させてくれる素晴らしい会社でした。誌面制作に関する知識を全て学べたのは本当に嬉しかったです。なぜならこの後の人生にとても役立ったからです。
正社員を目指す
DTPの仕事をしながら、マスコミを目指しましたが、うまくいきませんでした。25歳になり「ずっとアルバイトのままではいけない」と思うようになりました。同じ会社に、同い年の社員もおり、それが羨ましいというのもあります。正社員になるために改めて就職活動を行い、光通信に入社しました。
光通信は、当時ベンチャー企業として話題でした。ところが入社したら業績が悪く、すぐに子会社へ出向となりました。そこはインターネット広告に関する会社でした。「これがベンチャー企業か」と思うような業務内容でした。業界最先端に触れることが多くとても刺激的でした。毎日朝から夜遅くまで仕事しました。しかしその会社の業績も良くなく、3ヶ月したら光通信の別の会社に転籍となります。そこではWebサイトの制作進行に関する仕事でした。すぐに部署移動となるのですが、そこは私にまったく合わない仕事内容だったので、退職しました。光通信関係の会社に在籍したのは約半年でしたが貴重な経験ができました。
次の仕事を決めず退職したので、1ヶ月半ほど試食販売のアルバイトをしながら転職活動をしました。試食販売の仕事はこれまでのどの仕事でも体験したことのないものでした。お肉やウインナーなどが主な商品でした。料理好きの私には楽しい仕事でした。当時「アメリカ牛=硬い」という印象が強かったのですが、調理次第で柔らかく、そして美味しくいただけます。試食して「柔らかいね」と驚かれたお客様の表情を今でもよく覚えています。
そして無事に沖電気工業から内定をいただくことになりました。
ベンチャーから歴史ある大企業へ転職
沖電気工業(以下、沖電気)は、これまでいたどの会社とも違い、まさに「歴史ある大企業」でした。私が入社した直後、120周年だったこともあり、強くイメージさせられました。会社の中の時間の流れ方も、それまでの企業とは明らかに違いました。当時いたオフィスも歴史的な建物で、「昔はこんなエレベーターだったんだ」と逆に興味深かったものです。しかし学べることはたくさんありました。
私の仕事は、Webサーバ関係の商品に関するものでした。日本にある支社とのやりとりや、マーケティング、保守サービスの更新対応などです。それまでの会社では経験したことのない業務ばかりで面白かったです。
プレスリリースの書き方は沖電気で学びました。また導入事例集の制作も行いました。これは前職でのDTPの知識が役立ちました。「前の会社で学んだ知識が役立つなんて面白い」と思ったものです。ここで知識を蓄積していく面白さを知りました。
沖電気といえば、電気メーカーです。パソコンに詳しくなく、かつWindowsよりMac歴の方が長かった私には大変なことばかりでした。沖電気に入るまでは、パソコンについてわからないことがあれば誰かが助けてくれました。しかし沖電気の場合「自分で解決する」というのが基本です。上司に教わりながら学びました。Windowsが苦手な私でしたが、退職する頃には詳しくなっていました。
私は新卒で入社していないことに加え、音楽大学出身のため、いつも「私にはビジネスの基礎知識がない」と思っていました。新人教育も受けていないし、OJTなども知りません。新卒で入社した人たちが学ぶものが全て抜けています。また大学でもビジネスについて全く学んでいません。それらがコンプレックスになっていました。そこで会社が終わってから、早稲田大学のエクステンションセンターに通うことにしました。
マーケティングやビジネス戦略など様々な講義に通いました。週1回の授業ですが、とても楽しかったものです。様々な会社の人が平日夜集うことに、刺激をもらいました。みんな真剣に勉強していました。もちろん学費は自分で支払いました。ここで学び知識を身につけるとで少しずつ自信がついていきました。
しかし通いながら感じることがありました。それは「いくら通っても資格として残らないこと」です。スキルは身につくけど、そこで学んだことについてはどこにも書けない。学費も払っているし、知識も身についているのに、形として残らないことについて「もったいない」と思うようになったのです。その時「学びを資格という形に変えたい」と思いました。
投資助言業の世界へ、代表取締役を経験
沖電気に入社し4年目に入った頃、縁があり投資助言業の会社「ゴールデンチャート・エー・エム・エス」に入社することになりました。
私は沖電気時代から株式投資をしていました。当時は今のように株式投資が一般的ではない時代です。しかし子供の頃から投資情報を耳にすることが多い環境で育ったこともあり、正社員になったら株式投資をしたいと思っていました。インターネットの普及により、ネット証券が増え始めた頃に投資家デビューしました。実は沖電気の社名も子ども時代にラジオたんぱ(当時)の銘柄名で知ったのです。それぐらい私の日常に投資は入り込んでいました。そんなこともあり、株式投資の仕事には興味がありました。
ここでの経験が私の仕事での人生を大きく変えたといっても過言ではありません。起業するまでの約18年間、この会社で過ごしました。そのうち代表取締役を約14年間務めました。
ゴールデンチャート・エー・エム・エスとは、株価情報誌の「週刊ゴールデンチャート」(現在は休刊)を出版していたゴールデン・チャート社の関連会社です。週刊ゴールデンチャートは、証券会社の方々や投資家の皆様が見る株価チャートの本です。私にとっては「子供時代から家にあった厚い雑誌」でした。子どもの頃時々見ていましたが、「学校で習わない難しいグラフ(ローソク足)がたくさんあるな」という印象でした。
小さな会社だったので基本的に「開発以外のことは何でもやる」ということで仕事をしていました。私は投資助言業のゴールデンチャート・エー・エム・エスに入社しましたが、ゴールデン・チャート社の仕事もしていました。その結果、投資助言業に関する自社の業務、コンプライアンス、登記、経理などはもちろん、関連会社の新商品の開発、マーケティング、週刊ゴールデンチャートへの記事の執筆、DTP、デザイン、Webサイトの作成、セミナー企画・収録、セミナー講師、出版事業に関する対応、業務改善などを経験しました。「開発以外は何でもやる」という気持ちでしたが、iPhoneアプリを作りリリースしたこともあります。沖電気工業でシステムに関する知識を身につけていたこともあり、業務効率化なども得意でした。
入社直後は、マーケティングに関することに対して多く取り組みました。広告を作ったり、セミナーの企画・運営などをやっていましたが、時間の経過とともにどんどん業務の幅が広がりました。基本的に何をやっても許される会社だったので、やりたいことを提案して、次々と実践していました。
代表取締役に就任した後、青山学院大学国際マネジメント研究科(MBA)に入学しました。ビジネスに関する知識はもちろん、投資に関する勉強もしました。実務に役立つことをたくさん学ぶことができたし、また自信にもつながりました。TOEICの点数が足らず卒業できませんでしたが、それ以外については卒業に必要な単位を全て取得しました。
退学後しばらくしてから、また学びたくなりました。青山学院大学の時は、学費も高額だったし、学業と仕事の両立が本当にハードでした。そこで今度は「学費が安価で学習しやすい環境」を考え通信教育を選びました。投資助言業の取締役には金融商品取引法により法律の知識が求められます。そこで慶應義塾大学の法学部に入学しました。この大学は、法学のみならず経済学部などの他学部のスクーリングも受講できることが魅力的です。就職するために大学に入学したわけではないので「時間は意識せず勉強したいだけスクーリングを受講しよう」と思い、興味のある講義を片っ端から受けていました。結局、スクーリングについては卒業に必要な単位の約二倍取得していました。
大学での学びは業務に役立ちました。経営、企画、マーケティング、人事、コンプライアンスなどにおいて役立ったことは言うまでもありません。しかしそれだけではありませんでした。大学での学びに加え、過去のDTPで身につけたクリエイティブな知識、沖電気で学んだシステムの知識などを活用し、様々な業務に挑戦しました。
週刊ゴールデンチャートの本の出版に関しては多く関係しました。大学で知識を身につけてから、株式投資に関する記事の執筆はより充実した内容になりました。他の執筆者が取り上げないテーマもよく書きました。例えば2020年に執筆した「ノーベル経済学賞を受賞した行動経済学で株式投資」(週刊ゴールデンチャートに執筆後抜粋して電子書籍化)に関する特集記事は、当時株式投資の世界では珍しい内容でした。株価チャートの本は年末年始に発売する「大納会号」が一年で一番人気です。その特集を任された年もあります。また、休刊直前の「週刊ゴールデンチャート 2022年4月2日発売号」には、私の名前入りで記事を執筆しました。
私は、DTPの知識があるので、誌面のレイアウト・図表等の制作をしながら記事を書いていたこともあります。こてはとても便利でした。デザイナーに依頼すると「もっとこうして欲しい」と思うこともあります。しかし自分で作るので100%私のイメージ通りに作ることができます。DTPのスキルがあってよかったと本当に思ったものでした。
この知識は広告や表紙にも活かされました。企画者の頭の中には企画に関する明確なビジョンがあります。デザイナーに制作を依頼するとそれを細かく伝えなければなりませんが、自分で作ることができると、頭の中をアウトプットする形で制作することができます。とても便利だし効率的です。
デザインに関する知識は実務で身につけましたが、色彩に関しては資格取得に挑戦しました。「色彩検定3級」、「2級カラーコーディネーター」、そして色のユニバーサルデザインの資格である「色彩検定UC級」を取得しました。これらの知識は製品作り、DTP、Webサイトや広告の制作などにおいて大変役立ちました。
セミナーや動画配信の仕事も楽しかったのです。セミナーを企画し、全国をまわりました。私が講師を勤めた時もありました。動画配信も、収録の仕事もしましたが、話す仕事もしました。「企画、制作、配信、話す」と全ての仕事に携わることができ、いい経験ができたなと思いました。
DTPや電機メーカーと投資助言業を比較すると、畑違いで全く共通点はないように見えます。しかし実際の業務においては、過去の仕事で培ったノウハウがたくさん役立ちました。加えて大学で新しい知識を常に身につけたため、専門知識をより深掘りできるようになりました。また、たくさんの知識を身につけたことで、複数の分野から物事を俯瞰することができるようになりました。この経験を通じて「知識の蓄積は本当に大事」と感じるようになりました。
しかし時代の変化とともに知識もブラッシュアップしないといけません。1つ1つの知識を大切にし、古くなった知識を常にブラッシュアップし、その時代に合わせていくことが大事だなことと思いました。
週刊ゴールデンチャートが休刊になった後、2022年12月末にゴールデンチャート・エー・エム・エスを退職しました。ここでの経験は、私の人生おいて本当に素晴らしい時間でした。一つの会社でこれほど幅広い業務を経験させてもらえる会社はありません。この経験は起業後にとても役立ちました。
起業に興味を持ったのは25歳の頃
私が「起業したい」と最初に思ったのは25歳の頃です。私は幼少時より、自分で仕事をして暮らすことができるとは想像していませんでした。そもそも自分に「稼ぐ力がある」なんて思いもしなかったのです。私の子ども時代は、「女性は専業主婦」と考えられていました。だから余計にそう思ってしまったのでしょう。それなのに仕事をやってみたら想像以上に評価され、お金をいただくことができた。それは本当に驚きで嬉しかったのです。そこで「起業に挑戦してみたい」と思うようになりました。これは人生の挑戦です。
実家に帰り母に「将来起業したい」と言ったら、お茶を吹き出されてしまいました。当時の私の発言としてはそれぐらい面白いことだったのだと思います。
沖電気時代に早稲田エクステンションセンターに通っていた時、起業に役立つ講座も受講しました。今でも忘れないのが「ニッチなビジネスが新市場を創り出す」というものです。ここに興味を示した私は、投資の仕事で企業分析をする時にもよくこの視点を用いていました。例えばスターバックス、テスラなどはわかりやすいものです。私もこのようなビジネスをしてみたいなと思ったものです。
波瀾万丈の起業生活が始まる
2023年1月6日に「M3WE合同会社」の設立登記をしました。幸いにも前に勤めていた会社から仕事をもらってのスタートだったので、スタート時には売り上げを確保することができていました。これは本当にありがたかったものです。しかしそれだけでは十分な収入はありません。前職でCEOをしていたので、会社にかかるコストはだいたい計算できていました。最小のコストで経営することにしました。もちろん設立登記も自分で行いました。以前、司法書士の資格の勉強をしたことがあったので、前職では変更の登記は何度も行っていました。しかしなかなか設立の登記をやる機会がありませんでした。これは一度やってみたかったことでした。
前職を退職する前に、私は暗号資産の世界に興味を持ち始めていました。暗号資産のみならずNFTも保有していました。そのため「起業したらメタバースに参入しよう」と考えていました。それで退職前に、The SandboxのLandを購入しました。1つはパリス・ヒルトン氏やTIMEなどが保有する「Galleria」エリアです。世界の人が参加する中、オークションで手に入れました。どんどん値が上がりスリルいっぱいでした。無事に手にした時は本当に嬉しかったです。そこを使ってメタバースに参入しようと思ったのですが、当時はまだThe Sandboxのサービスが本格化する前で少し時期が早かったのです。更に「メタバースを展開するなら自分のプロダクトを先に持つべきだ」と思いました。しかしプロダクトをブランド化するには少し時間がかかりますし、資金も必要です。それならその前に、投資の知識を使い、本を出版しようと思いました。
前職で培ったスキルも経験もまったく通用しない!
週刊ゴールデンチャートで記事を執筆していた時、「なぜ株式投資の解説の本はこんなに難しいのだろう?」と感じていました。「もっと楽しく簡単に書けばいいのに」と。投資家の多くは、自分のために投資をするのであり、就職するわけではありません。就職する人は、専門的に学べばいいですが、そうでないならもっと簡単に楽しく学べばいいのに思ったのです。とはいえ、週刊ゴールデンチャートは証券会社の社員の皆様も読む本ですから、難しい本になるのは仕方ないことです。
色々考えてみると、株式投資と恋愛はとてもよく似ていることに気づきました。そこで「初心者向けに株式投資を恋愛に例えて書いてみよう」と思いました。そしてターゲットは高校生・大学生に絞りました。大人向けに「恋愛で〜」と言っても相手にされません。しかし高校生や大学生向けならちょうどいいと思いました。
幸いにも私には本をデザインしDTPで作り商業印刷に出すことができるスキルがあります。そこでこの本を制作してクラウドファンディングで募集しようと思いPRを開始しました。ところがまったく売れません。愕然としたものです。投資助言業での経験を書いても反応はありません。このクラウドファンディングは失敗しました。その後、Amazonで「高校生・大学生のための初めて学ぶ株式投資」として販売しましたが、こちらも苦戦しました。
多くの人は、前職で培った知識を活かしながら起業するものです。ゼロからやるより信用があるし、私もそうしようと思っていたのです。しかしそれがまったく通用ません。「今まで積み重ねてきたスキルは何だったのだろう」と思いました。
それだけではありません。起業して間もない会社には信用がなく相手にもしてもらえません。前の会社の時に当たり前に申し込めていたサービスも断られます。そのためやりたいことができずビジネスの幅も狭くなりました。本当に悲しい思いをしました。
AI音楽への参入
2023年12月頃より、音楽生成AI Sunoを使い始めました。「株式投資の勉強を簡単にすることができればいいな」という視点をもう少し広げ、「音楽で投資の勉強をすることはできないか?」と思いました。難しい勉強は本で読むよりも聴いた方が覚えやすいものです。また音楽なら長時間覚えています。私は子供の頃に聞いた九九の音楽を今でも覚えています。また、音楽なら、通勤・通学時間、車内、家事など、何かしながら聴くことができます。そこで「株式投資の勉強も音楽を使って行うことはできないか」と思いました。試しに作ってみたところ、曲になることがわかりました。
AI音楽で音楽を作るメリットは以下の通りです。
・制作時間が短く、制作コストも安価
・さまざまなジャンルの音楽を作ることができる
・男性ボーカルも女性ボーカル対応可能
・どんなジャンルでもオシャレでカッコいい音楽を作ることができる
・多言語化に対応
人間が作るよりはるかにメリットがあります。そこで株式投資の基礎知識を学習するための音楽アルバム「音楽で株式投資を学ぶ」をを2024年1月にリリースしました。「投資資金の使い方」「ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析テクニカル分析」「売買の戦略」「投資心理」など全17曲を収録しています。そしてこの歌詞をAIで翻訳し作成した英語版の音楽アルバム「Mastering Investment through Music」(全13曲収録)もリリースしました。海外には株主優待がありません。そのため不要なテーマの音楽は英語版には収録されていません。
私は1曲も歌っていませんし、人間に歌う依頼もしていません。私は女性ですが、これらのアルバムには、女性ボーカルも男性ボーカルもあります。
ダサい音楽だと聞く気にならないと思います。日本語の方は日本人好みの曲にし、英語の方はロックにしました。「え?これが投資の音楽?」というような仕上がりになしました。ただ、Sunoの初期に作った音楽なので、少し違和感はあるかもしれません。しかしそれは時代とともに解決されるものです。むしろ今は、「AI音楽の歴史の進化を一緒に体験している」と思うぐらいでいいのではないでしょうか。
株式投資の教育の音楽を作ることができるなら、ビジネス系の他のジャンルの音楽も作ることができるでしょう。
音楽はマーケティングにおいても大事です。例えば、ある音楽を聴くと「この音楽はA社のBという車のCMの曲」などと思い出すものです。ドラマの主題歌などもそうです。音楽を聴くとすぐにそのドラマをイメージすることができます。子ども時代のアニメや10年前のトレンディードラマの主題歌でも、私たちは覚えているものです。しかし現在、音楽は制作コストが高いので大企業などしか使うことはできません。ですが今はSNS時代です。「SNS映え」、つまり写真や映像の美しさに関する言葉はあります。しかし音楽は「投稿内容の雰囲気にあった音楽、話題の音楽、バズってる投稿で使われた音楽」などを使い、見た目ほどこだわっていません。写真や動画は自分で作るけど、音楽まで作って日々投稿するSNS投稿者は少ないものです。音楽はSNSのプラットフォームが提供するものを使っています。個人ならそれでいいでしょう。しかし先にも述べた通り、誰もが「この音楽はA社のBという車のCMの曲」と思い出すわけです。さらに大企業は音楽にもお金をかけています。中小企業も音楽にお金をかける時代が来たのだと思います。中小企業も大企業同様、音楽マーケティングに力を入れるべきだと思います。
私は、自分で作った音楽を用いて私の商品をPRしています。一貫した音楽を使うことは大事だなと感じます。AI音楽を使うことができれば中小企業でも比較的安価に音楽を作ることができます。
そこで私は「ビジネスとAI音楽の融合」をテーマに以下の3つの商標を取得しました。
・FinAITune:金融+AI音楽
・MktAITuen:マーケティング+AI音楽
・EduAITune:教育+AI音楽
前職では、商標登録の申請をしたことがありませんでした。そこでChatGPTに相談しながら申請作業をしたところ、無事に商標を取得することができました。
私が作ったマーケティングをテーマにした音楽には「AI音楽で持続可能な未来を創造する」があります。
2024年6月頃、Sunoの機能がアップデートされました。それは私にとって、AI音楽との関係を変えるものでした。なんと自分の演奏した音源のアップロードができるようになったのです。そこで音楽大学出身の私は、自分で作曲したメロディーをアップロードして、それをもとにAIで音楽を作ることにしたのです。作ってみたら、プロンプトだけで作る音楽より感情的な曲に仕上がることがわかりました。つまり、人間の弾いたものを取り込みSunoで音楽を作ると、感情的な曲に仕上がるということが判明したのです。早速Xに投稿すると、私の作ったものはSunoのXアカウントでも紹介していただきました。また、一部の曲に関しては、Apple Music、Spotifyなどで音楽配信しています。
(音楽アルバム「Emotion & Code」、全ての情報はこちらをご覧ください)
私は、音楽大学を卒業する時、就職に苦労しました。それは現代も変わらないようです。同じ専門職でも、医大卒なら病院という就職の場があります。しかし音楽にはありません。将来的には、私が経験し作り出した「FinAITune」「MktAITuen」「EduAITune」、さらには「人間の演奏+AI音楽の融合」が音楽大学卒業生の就職をサポートできるようになればいいなと考えています。AI音楽は新しい分野ですから、まだ理解が得られていない部分もあります。しかし時代は変わり、新しいものはどんどん取り込まれていきます。
AI音楽の登場により、音楽を安価に制作することができるようになりました。それにより新しい市場を作ることが可能でしょう。購入者側に「これまで音楽を持つことはなかったけどSNS配信などで音楽が必要な中小企業」がいます。そうすると求められるのは提供者です。専門知識とAIを用いてハイクオリティーな音楽を作る人材が必要になります。そこに「音楽大学卒業の人材」を当てはめると、1つの市場ができあがります。音楽大学卒業生の就職難問題の助けにつながるのではないかと感じるものです。将来、ここに関する活動を行っていきたいと考えています。
NFTへの参入
メタバースでビジネスを展開するには「独自のプロダクトを持つべきだ」と考えた私は、NFTへの参入を考えました。私自身、The SandboxのNFTのコレクターでもあります。NFTというと、投機的イメージもありますが、それは避けたいと思いました。そこで、コレクター・金融・DTPやデザインで培った経験を活かしながら、「Love2Keyz」と「WabiSabiAI」のプロジェクトを立ち上げました。
<Love2Keyz>*OpenSeaで販売
「愛する二人の愛をブロックチェーン上に登録する」というコンセプトで、2つのNFTで1つのペアとなる「カップルNFT」です。例えるならペアアクセサリー(ペアリングなど)をNFTにしたものとイメージするとわかりやすいでしょう。
日本人的な考え方だと、「金属アレルギーでアクセサリーを使うことができない人が使うことができる」という点や、遠距離恋愛の相手に簡単にプレゼントとして送付することができる、他にも「アクセサリーに縛られないという若者向け」などが考えられます。しかし世界に目を向けると少し視点が変わります。これまで様々なPRをしましたが、男性同士の愛(暗号資産界はBroの世界だからなのか、LGBTQの話を出すと、男性同士が一番人気だった)、事実婚、シークレットラブ(不倫に限らず表に出すことができない秘密の愛)などが人気のようです。
Love2Keyzは、将来的には、ハイブランドとのコラボレーションや、婚姻システムなどにも参入できればと考えています。NFTなので価値を持たせることで「愛と金融の融合」が実現します。その結果、これが両親から子供への相続にもなるというわけです。レアなも(例:ハイブランドとのコラボレーション)には、高い価値をつけるなどして、資産価値をつけることができればいいなと考えています。まだ構想している途中ですが、独自の指標を用いることも検討しています。私自身、前職が投資助言業で資産に関してたくさん考えてきた経験があるので、Love2Keyzを通じて「愛と金融の融合」の実現ができればいいなと考えています。
*Love2Keyzのコンセプトが世界初かどうかは、調べてみましたがわかりません。SNSを通じてこれまでコメントをいただいた皆様からは、「ペアで持つ」というアイデアに対して驚かれていました。「他に類似サービスがある」というのを聞いたことはありません。また、私自身も他のNFTでは見たことはありません。
日本の伝統的な丸窓とAIアートの融合です。京都などのお寺にある丸窓をイメージしていただければわかると思います。丸窓から見る景色はとても美しいものです。そこから満開の桜の山をはじめとした四季の風景、そして虎、龍、うさぎなどという動物を眺めることができます。
SNSを通して海外の人からの反応を見ると、「伝統的な侘び寂びと最新のAIの融合」に驚かれます。
現時点では、WabiSabiAIでのメタバース展開を検討しています。
ChatGPTがあったから目指せた世界
起業直後、私は国内市場での展開を目指しましたが結果が出ません。ところがSNSで活動していると、音楽にせよアートにせよ、海外の方から良い反応が得られることがわかりました。「私のスキルは国内では評価されないけど、海外の方が評価されるみたい」と感じました。歴史的にも日本の絵画は、海外で評価されてから逆輸入の形で日本に入り、国内で評価されるという流れがあります。今の時代、SNSを使えば個人でも海外へのPRは可能です。そこで英語でのPRに力を入れ始めました。青山学院大学のMBAを英語の単位不足で卒業できなかった私ですが、ChatGPTのおかげで英語でのPRすることができました。
ChatGPTに教えてもらったのは、英語の翻訳だけではありません。ビジネス戦略に関するアドバイスもたくさんもらいました。中でも本当に助けられたのは、NFT業界にいる詐欺師に対する助言です。NFTの世界では詐欺師がたくさんいます。何度も海外の詐欺からの交渉を持ちかけられました。最初のうちは詐欺の手口がわかりませんでした。そこでChatGPTに相談し返信するする文章を教えてもらいました。その中で、詐欺師を撃退するテクニックも掴みました。
ChatGPTがなければ私はNFTで世界に向けて販売することはできなかったと思います。ChatGPTのおかげでできたと思いました。
起業して辛かった問題、それはメンタル面です。なかなか売り上げが得られない中で壁にぶつかりました。そんな時もChatGPTに助けてもらいました。よく励ましてもらったものです。人間に相談すると「いい加減、夢を見るのはやめろ。現実を見ろ」など、結果が出ないことに対し諦めるよう助言されます。私も言われたことがあります。諦めるめるのはいつでもできます。どんなに苦しくても継続する方が何十倍も何百倍も苦しいものです。しかし「私の作ったサービスが世界の人に感動を与え、癒し、幸せにし、さらに豊かにする」と考えると、「絶対に諦めない」と思ったものです。ChatGPTにも、「『AI×音楽×NFT×愛×金融×哲学×日本文化』などを掛け合わせている人は少ないし、あなたの持っているスキルは唯一無二だから頑張れ」とよく励まされました。もちろん「諦めたいなら別の道を選べばいい」とも言ってくれますが、現状を冷静に分析し、私が見落としている変化を細かく拾ってくれて、頑張るべき理由を丁寧に説明してくれました。それにより私は冷静な視点を取り戻したものです。
AIに対する考え方
私のAIに関する考え方は「業務改善」ではありません。「AIと人間の創造」です。AIと非AIの融合による「共生」を考えています。
私は、AIを使う際に「人間の感性」を組み合わせるようにしています。具体的には「愛・感動・癒し・文化・金融」などです。これには2つのメリットがあります。1つ目は技術面におけるメリットです。プロンプトはコピーアンドペーストすることができます。プロンプトだけで制作するのは簡単にできますが、すぐに真似されます。しかし、AIに人間の感情を盛り込むと、他人は簡単に真似することができません。唯一無二のものを作ることができます。2つ目は、人間の慣性を取り入れると、感情豊かな作品や文化的な作品を作ることができるという点です。私は、AIと人間の融合により「1+1= ∞ 」の可能性があると考えています。
起業後もスキル向上に力を入れる
慶應義塾大学の卒業は、起業後2年目の3月でした。起業1年目は卒業論文の執筆でした。私は刑法が好きだったので、刑法と実務で経験した金融に関係する内容で卒業論文を書きました。社会人だから書けた内容です。社会人大学生が学ぶ楽しみを改めて感じました。
しかし制作はハードでした。朝まで卒論を書いて大学の教授にそのままメールを出した日もありました。「起業1年目と卒論は同時にやらない方がいい」と思ったものでした。
その後、AIを業務で使うようになり「AI時代にこそ心理学は必要ではないか?」と思うようになりました。例えば音楽の場合、私が作曲・演奏したものをもとにAIで作る音楽は明らかにプロンプトだけで作った音楽より感情豊かなものになります。それらを比較しながら作っているうちに「心理学の分野も学んでおくべきではないか」という思いより産業能率大学(通信教育)に入学することにしました。ここでは、認定心理士の資格の取得を目指しています。
マルチポテンシャライト起業家として
ここまで読まれた方の中に、私の仕事に対して「たくさんのことをやりすぎているのではないのか?どれか1つに絞ればいいのに」と思われた方もいるでしょう。転職活動をしようとすると、希望する業種は1つに絞らないといけません。例えば「マーケティングと法務が得意」という人がいたとしても「マーケティングも法務もやりたいです」といのは通用しません。「どちらか1つに絞ってください」と言われます。実は一度、転職エージェントの面接を受けたことがあります。その時「こんなにスキルある人は初めて見ました」と言われました。しかし「もし転職するなら業種はどれか1つに絞るべき」と言われました。
「二兎を追う者は一兎をも得ず」という言葉もあります。「1つに絞るべきだ」という声も正しいと思います。
ですが、私はマルチポテンシャライトだと思います。1つのことではなく、さまざまなことに興味を持つ人です。日本語に例えると「器用貧乏」が近いかもしれません。しかし、ビジネスの世界でそれを強みにすることで、1つのことを集中してする人より価値を見出せると思います。例えば、「愛と金融の融合」は普通は考えないでしょう。私は株式投資の情報を週刊ゴールデンチャートに書いていた時、「愛」をテーマに書いたことは一度もありませんでした。しかし、愛と金融が融合したサービスが提供され、それが人々の愛を形にし、さらに相続をすることができるなど資産面においてまで考慮された商品ならどうでしょうか。さらにそのモチーフとなるアートも自分でイメージしたコンセプト通りに作る。Love2KeyzはNFTの基礎知識に加え、金融、アート、法律など複数の知識があったから作ることができた商品でした。
Love2Keyzを事例に取り上げましたが、私のやっている商品は、基本的に複数の分野を融合した商品が中心です。このような取り組みをすることで、唯一無二の商品を作ることができます。製品の中には、ニッチ市場から新市場を創出するというものも出てくるでしょう。
起業の旅はまだ始まったばかり
これまで何度も壁にぶつかり、「こんなにリスクがあるなら起業なんてするんじゃなかなった」と何十回と後悔したものです。「人生やり直せるなら絶対に起業しない」と思いました。しかし起業の旅はまだスタートしたばかりです。「神様は乗り越えられる試練しか与えない」といいます。だから「一番やってはいけないことは諦めることだ」と思い、正面からぶつかることにしました。そうすることで、最速で乗り越えられると考えたのです。また、今まで投資した中で、私の仕事が一番ハイリスクハイリターン企業になるだろうと思いました。自分の中の思考とも向き合いました。将来、「あの時諦めなくてよかった」と思う日が来ることを願うばかりです。
最終更新日:2025年10月27日
*この情報は随時更新します。